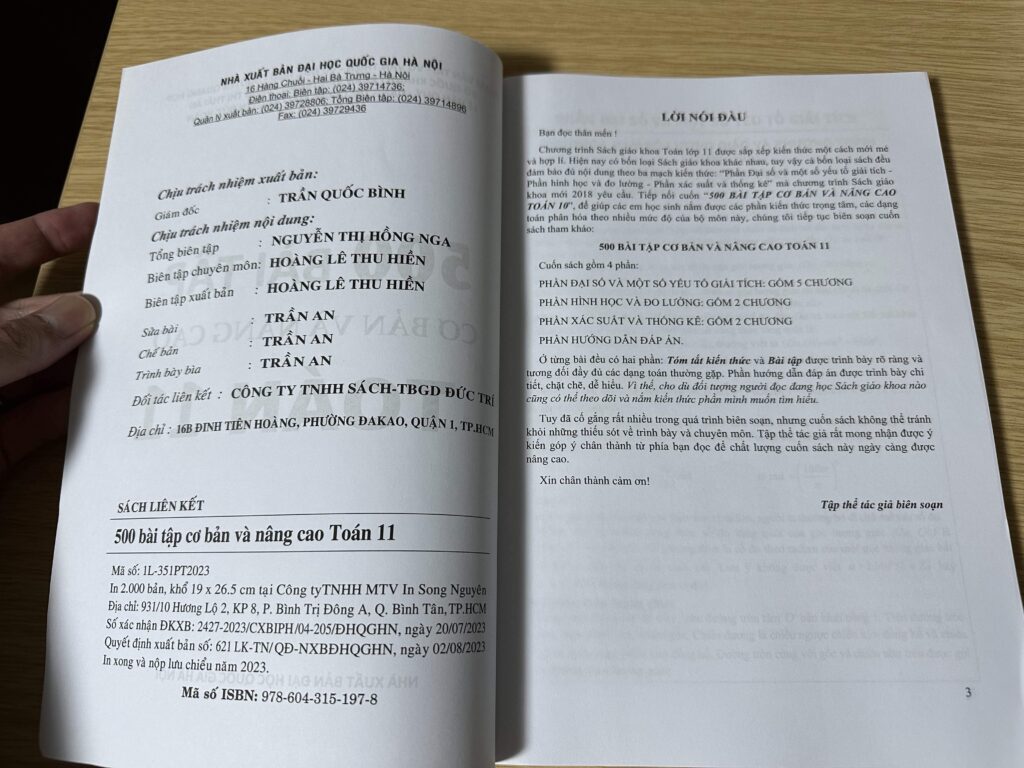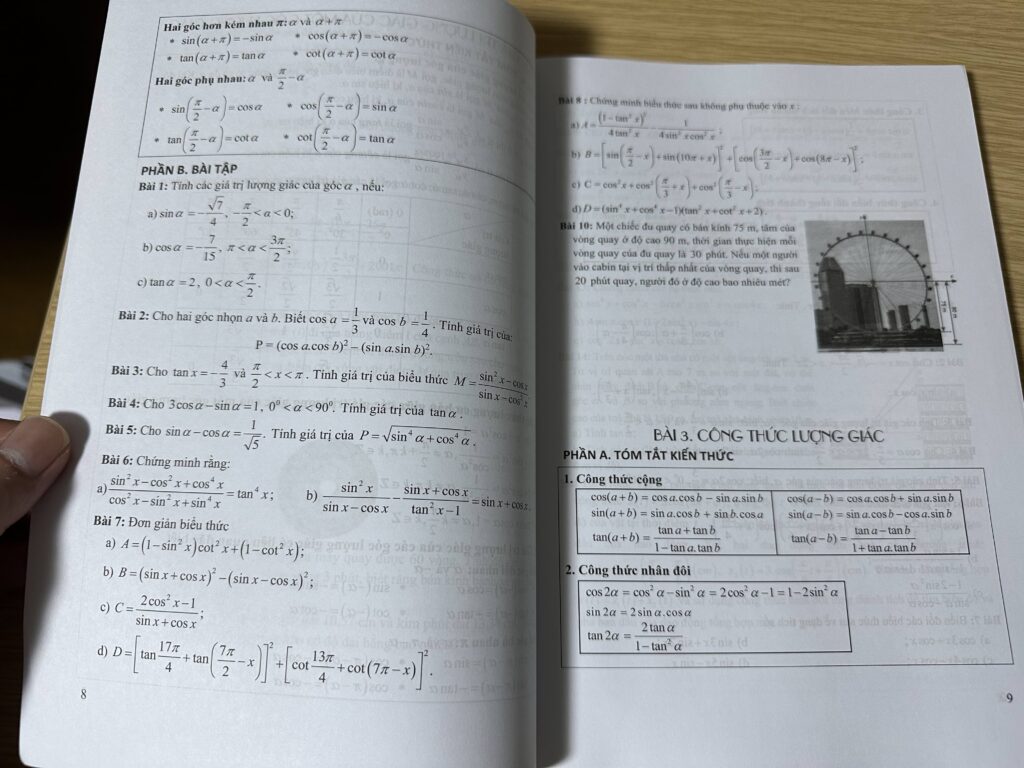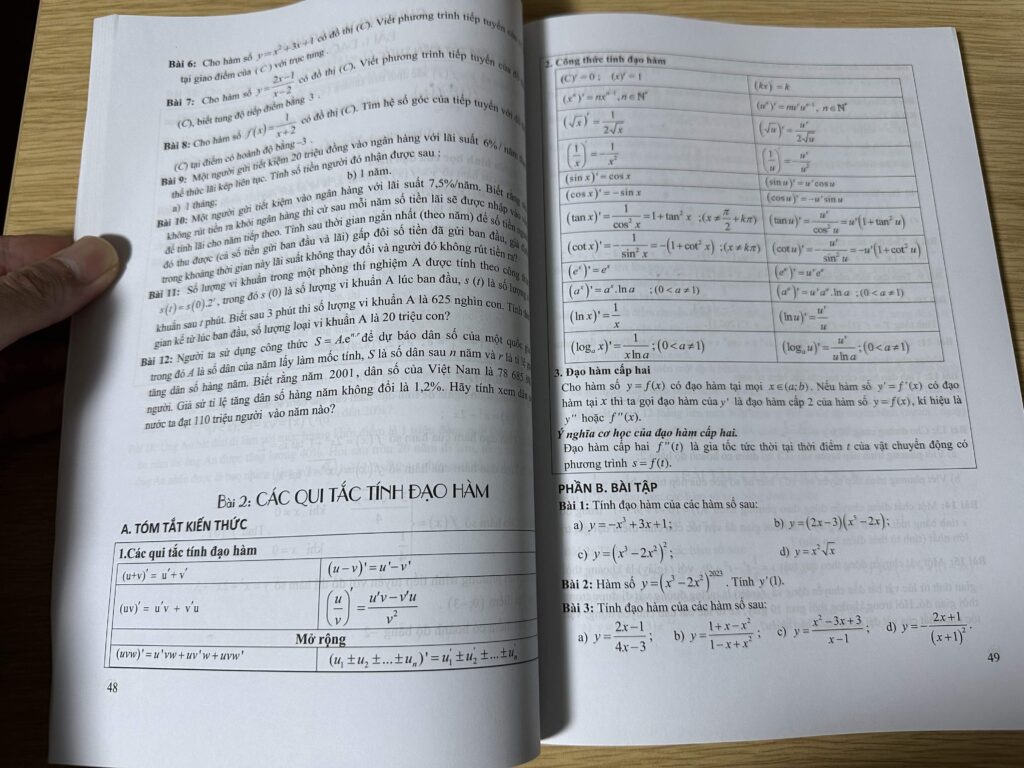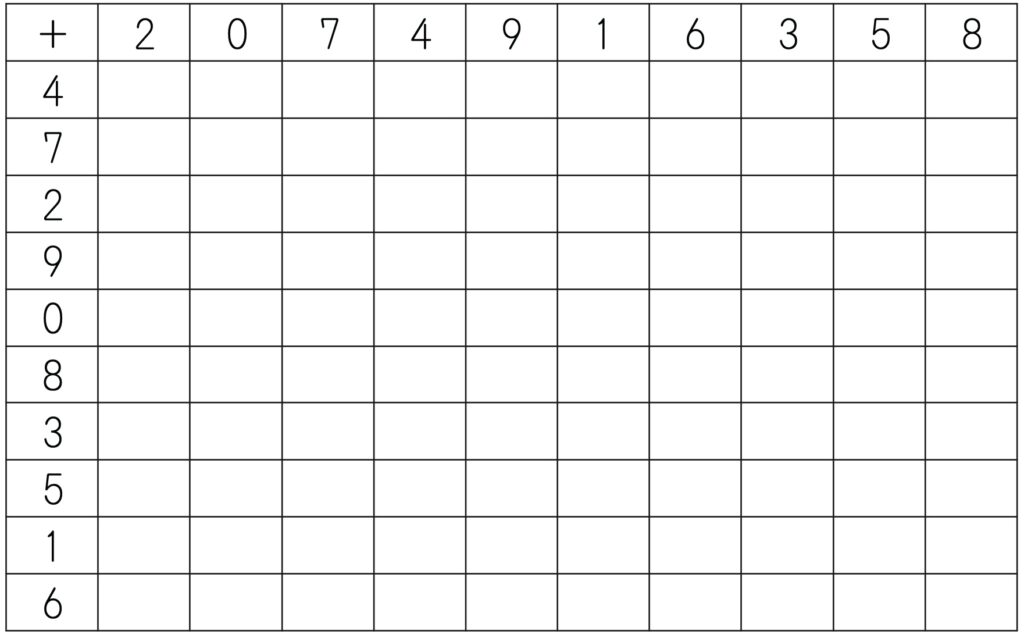公開日 2024/07/24
梅雨も明け夏本番ですね。
受験生には大事な時期です。
受験の天王山とも言われますが、なぜ大事なのか?
「休み」があるからです。
学校の良いところを一つ挙げると、それは
生活リズムが整うことです。
日々の生活、習慣が人を作ります。
学ぶ習慣のないまま過ごしてきた人は、新しいものに対して最初から抵抗するようになりますし、
運動習慣のある人は死ぬ直前まで生き生きとしています。
私が通っているプールには、もう70であるのに我々世代よりも速く泳いだり、自己ベストを更新する方々がおられます。本当に頭が上がりません。
学校があることで一定の生活リズムが出来上がり、健康に成長していることを忘れてはなりません。
夏休みは、生活リズムが崩れやすいです。
崩れると、勉強時間が減ります。身体がよく働きません。
だから差がつきやすい。
つまり夏休みで最も重要なのは、
学校へ通っている時と同じ生活リズムを維持することです。
どう維持するか
何を維持するかというと、
起床時間
食事時間
就寝時間
この3つを特に守りましょう。
夜更かししてしまって就寝時間が遅くなっても、起床時間を遅らせないようにしてください。
その分は30分以内の昼寝で取り戻します。
継続するのに必要なのは、自分の意思ではありません。
環境です。
今は夏休みのラジオ体操はあるんでしょうか?
ポイントは、自分だけでなく、他人を巻き込むことです。
朝に他人との約束を入れておくと良いです。
例えば、友達と図書館に集合するとか、オンラインでお互いに勉強開始を報告し合うなど。
遅れたら昼食を奢らなければならない、などのルールを設定しておくと良いですね。
1人で続けるのは難しいです。
チームを組んだほうが成功する確率は上がります。
ただし、一方的に依存してくる人と組むのはNGです。
発明家、トーマス・エジソンの言葉を載せておきます。
Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.
我々の最大の弱点は諦めることだ。成功するのに最も確実な方法は、常にもう一回だけ試してみることだ。