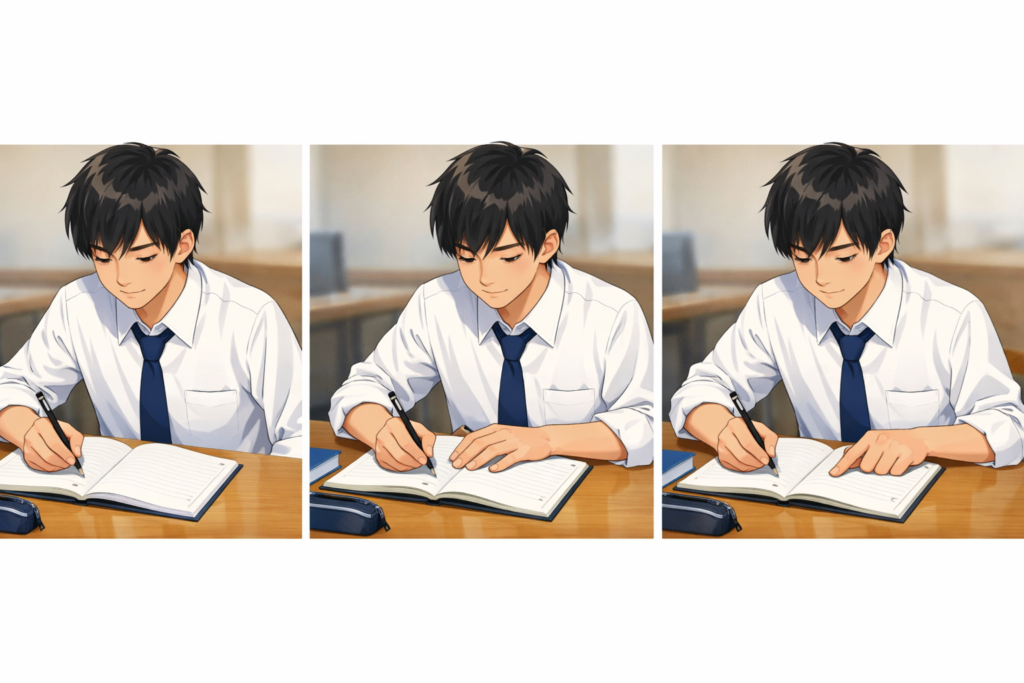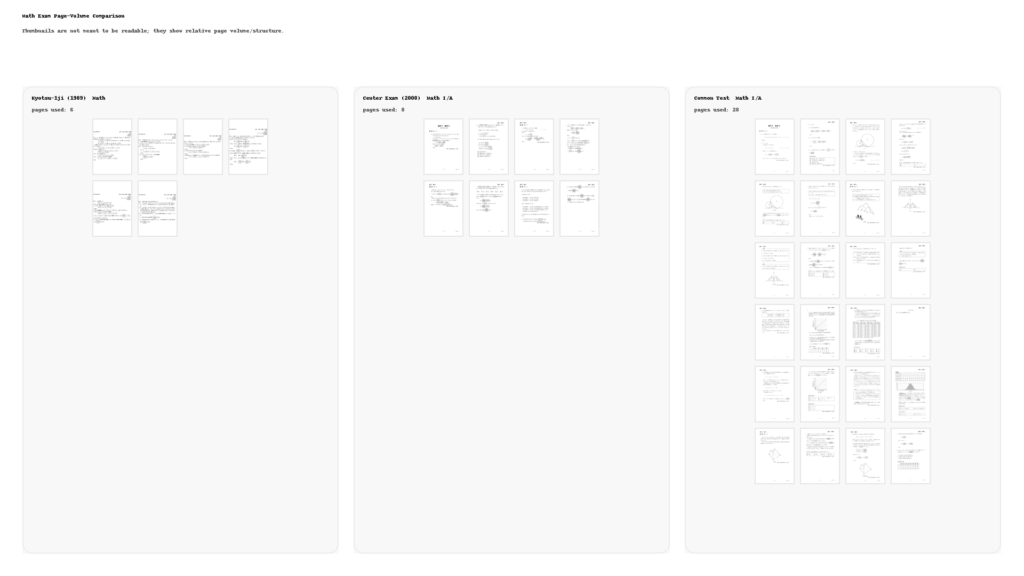公開日 2026/02/06
国公立大の一般選抜の志願倍率が出ています。
難関10大学(北大、東北大、東大、東科大、一橋大、名大、京大、阪大、神大、九大)では、東大理系や東科大(旧東工大、東京医科歯科大)で昨年比減少、一橋昨年比増以外は概ね変わらず、共通テスト平均点下落のインパクトは思ったほど強くはないようです。
(参考:データネット2026)
県内を見ていきましょう。
長崎大です。
【長崎大学】2026年度 一般選抜(前期日程)志願倍率まとめ(2/4 17:00時点)
出典:長崎大学「令和8年度一般選抜志願状況(2月4日17時現在)」。
| 学部 | 学科・区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|
| 多文化社会学部 | 多文化社会学科 | 72 | 168 | 2.3 |
| オランダ特別 | 3 | 5 | 1.7 |
| 小計 | 75 | 173 | 2.3 |
| 教育学部 | 小学校 | 71 | 135 | 1.9 |
| 中学校教育コース(文系) | 15 | 34 | 2.3 |
| 中学校教育コース(理系) | 14 | 45 | 3.2 |
| 中学校教育コース(実技系) | 5 | 14 | 2.8 |
| 中学校教育コース 計 | 34 | 93 | 2.7 |
| 幼児 | 10 | 26 | 2.6 |
| 特別支援 | 11 | 24 | 2.2 |
| 小計 | 126 | 278 | 2.2 |
| 経済学部 | 総合経済学科 | 190 | 478 | 2.5 |
| 医学部 | 医学科 | 66 | 502 | 7.6 |
| 保健学科(看護) | 50 | 131 | 2.6 |
| 保健学科(理学) | 24 | 67 | 2.8 |
| 保健学科(作業) | 14 | 37 | 2.6 |
| 保健学科 計 | 88 | 235 | 2.7 |
| 小計 | 154 | 737 | 4.8 |
| 歯学部 | 歯学科 | 40 | 94 | 2.4 |
| 薬学部 | 薬学科 | 32 | 129 | 4.0 |
| 薬科学科 | 36 | 71 | 2.0 |
| 小計 | 68 | 200 | 2.9 |
| 情報データ科学部 | 情報データ学科(選抜A:45人/選抜B:128人) ※志願者内訳。倍率は学科全体(計) | 70 | 173 | 2.5 |
| 小計 | 70 | 173 | 2.5 |
| 工学部 | 工学科 a方式 | 151 | 374 | 2.5 |
| 工学科 b方式 | 47 | 257 | 5.5 |
| 小計 | 198 | 631 | 3.2 |
| 環境科学部 | 環境科学科(選抜A) | 40 | 93 | 2.3 |
| 環境科学科(選抜B) | 40 | 122 | 3.1 |
| 小計 | 80 | 215 | 2.7 |
| 水産学部 | 水産学科 | 60 | 152 | 2.5 |
| 合計(前期日程) | 1,061 | 3,131 | 3.0 |
経済学部や工学部のa方式など、昨年2倍を切っていた学部はかなり上がりました。
皆考えることは一緒ということです。
教育学部も志願者数が倍になったところもありますね。
募集人員が少ない学科、コースはそもそも倍率が変動しやすいという点には注意です。
医学部はさすがの人気ですね。
今年もきれな隔年現象が起きています。来年は5倍台でしょうか。
情報データ科学部も同じく隔年現象です。
【長崎県立大学】2026年度 一般選抜(前期日程)志願倍率まとめ(2/4 10:00時点)
出典:長崎県立大学「令和8年度 一般選抜 志願状況(令和8年2月4日 10時時点)」。
| 学部 | 学科・区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|
| 経営学部 | 経営学科 | 70 | 272 | 3.9 |
| 国際経営学科 | 30 | 41 | 1.4 |
| 学部計 | 100 | 313 | 3.1 |
| 地域創造学部 | 公共政策学科(前期計) | 60 | 290 | 4.8 |
| └(英語) | 40 | 195 | 4.9 |
| └(数学) | 20 | 95 | 4.8 |
| 実践経済学科(前期計) | 65 | 245 | 3.8 |
| └(英語) | 25 | 77 | 3.1 |
| └(数学) | 40 | 168 | 4.2 |
| 学部計 | 125 | 535 | 4.3 |
| 国際社会学部 | 国際社会学科 | 30 | 96 | 3.2 |
| 学部計 | 30 | 96 | 3.2 |
| 情報システム学部 | 情報システム学科 | 20 | 55 | 2.8 |
| 情報セキュリティ学科 | 40 | 97 | 2.4 |
| 学部計 | 60 | 152 | 2.5 |
| 看護栄養学部 | 看護学科 | 38 | 138 | 3.6 |
| 栄養健康学科 | 24 | 70 | 2.9 |
| 学部計 | 62 | 208 | 3.4 |
| 大学計(前期日程) | 377 | 1,304 | 3.5 |
長崎県立大学は一見するとすごく倍率が高いですが、すこしからくりがあります。
例えば経営学部経営学科は、志願倍率3.9となっており、これは昨年同時期のものとほとんど変わりません。
しかし、令和7年度入試の結果を見ると、実質倍率は2.9です。
これは、受験者数が減ったためで、出願から前期試験までの間に例えば長崎大の学校推薦入試の合否発表があります。長大の推薦+前期県立大という選択をしていた生徒が長大推薦に合格すると、県立大は受験しません。
別の私立に合格して受験を辞退した生徒もいるでしょう。
このような理由で実際の受験者が大きく変化することがあります。
地域創造学部公共政策学科は明らかに倍率上昇ですね。
昨年低かったので当然です。