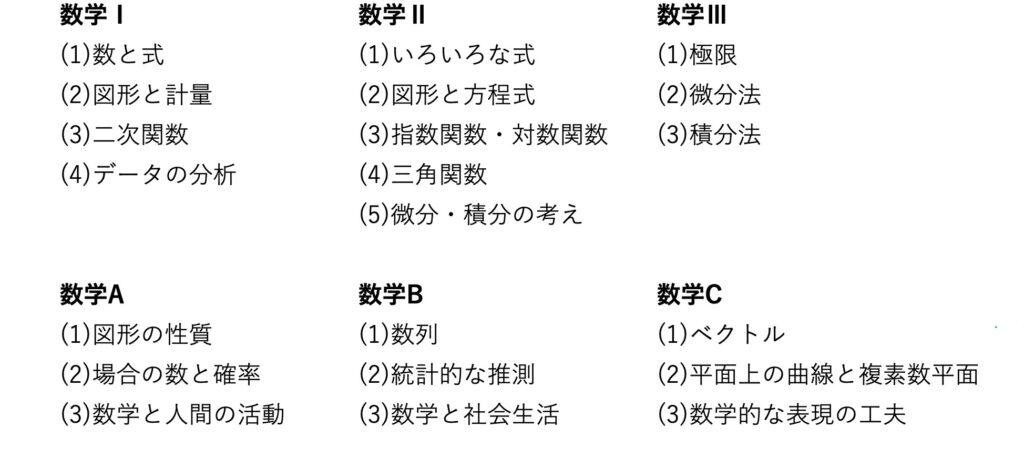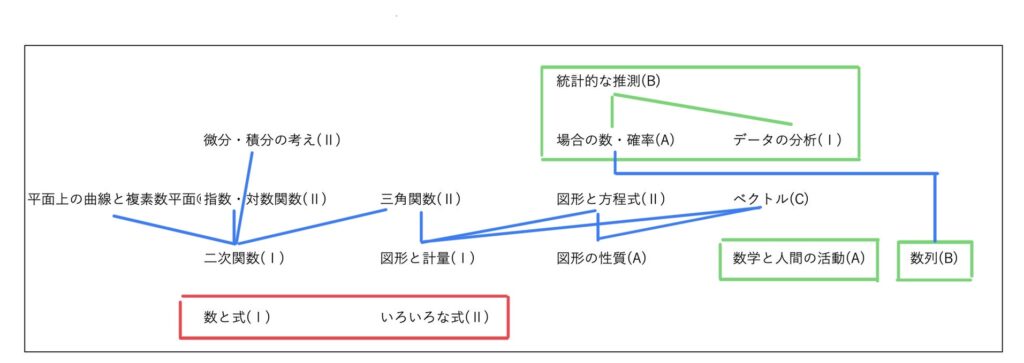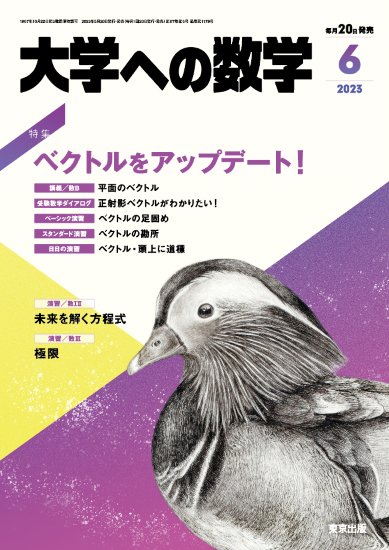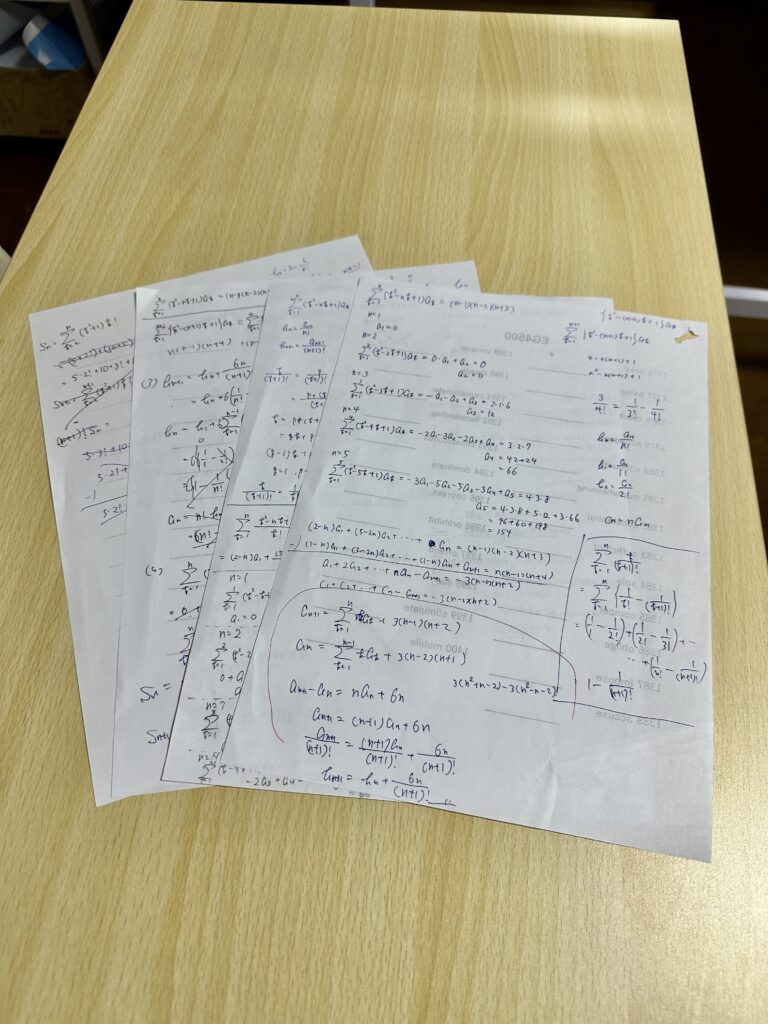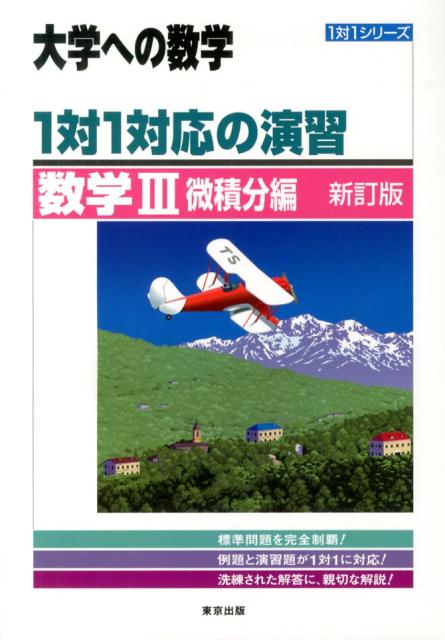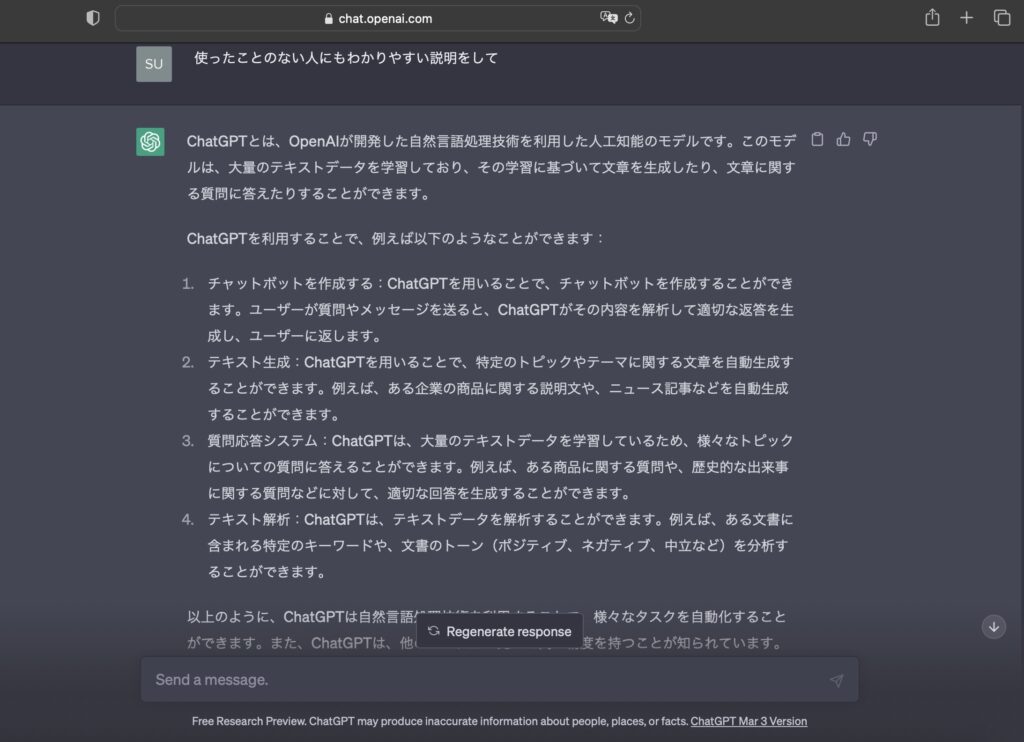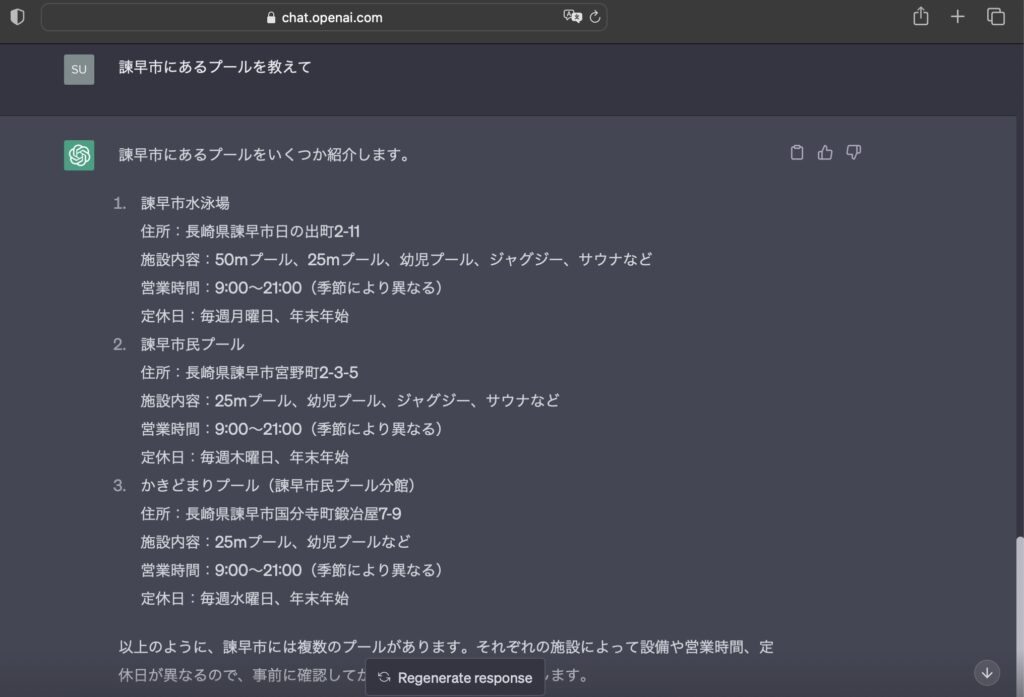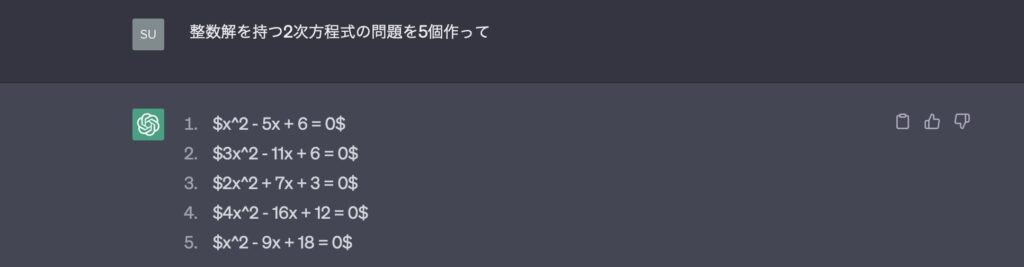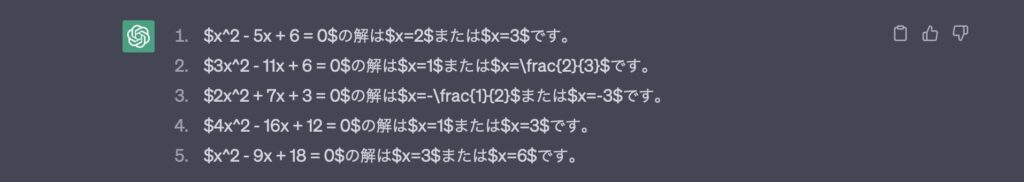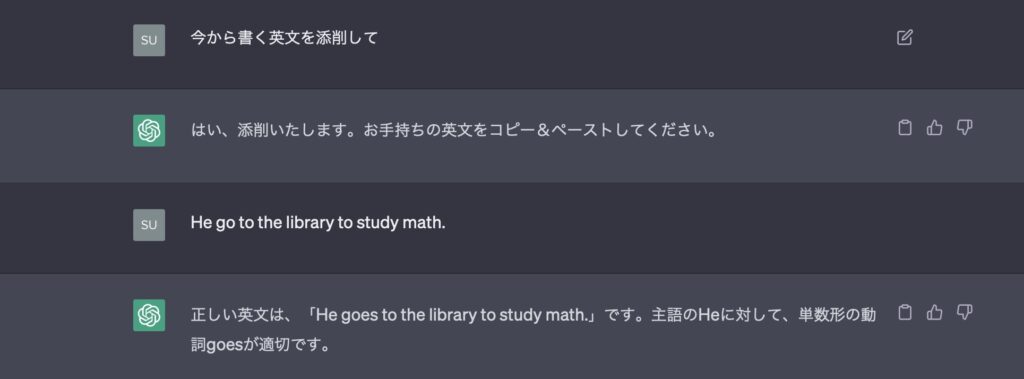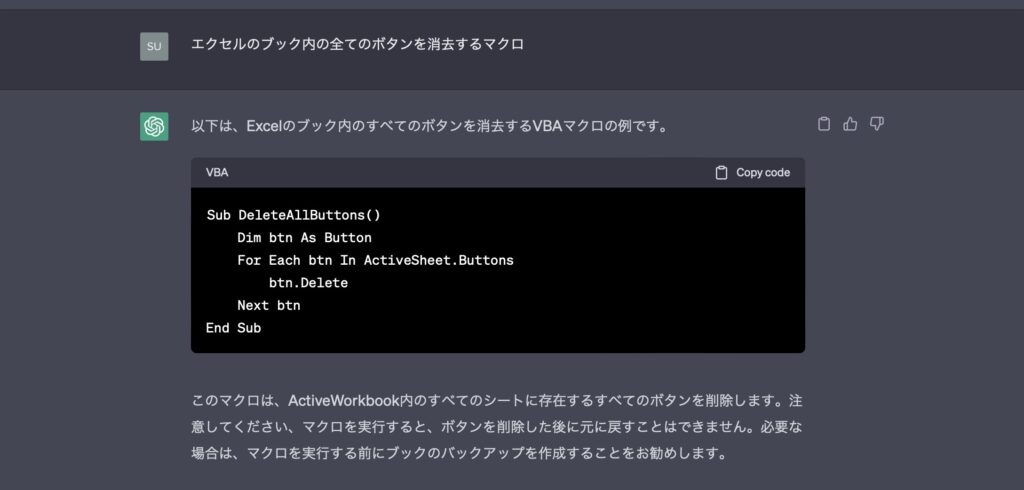公開日 2023/07/12
仕事ができるとかできないとか言うのは、
頭が良いとか悪いとか言うくらい意味のない議論ですが、
それほど仕事を上手にこなせるかどうかというのは多くの人にとって関心があることです。
今回は中学生高校生向けに、将来仕事が上手にできるかどうかはすでに決まり始めている、と言う話をします。
会社は学校ではない
まず知っておかねばならないことは、
学校と会社は目的が全く異なるところだということです。
学校は「勉強を教わる」または「教える」ところです。
会社は「利益を追求する」ところです。
学校ではあなた方生徒は、自ら行動せずとも時間割に従って、先生に従って勉強していれば何も文句は言われません。(むしろ勝手なことをすると怒られることもありますね。)
一方会社というのは、偉い人に従って働くわけですが、1から10まで丁寧に教えてもらえることを期待してはいけません。
もちろんゼロからいきなり仕事を振られるわけではありませんから安心してください。
基本的には先輩から少しずつ教わったり、余裕のある会社はしっかりした研修制度があります。
ただ、学校のように丁寧に復習してくれるわけでもありませんし、わからないことは自分で聞かねばわからないままです。
会社はあくまでも、求められるサービスや製品を提供して利益を得るのが目的であり、教育機関ではないからです。
良い社会人になるためにできること
この項では子どものうち、学生のうちにできるようになっておくと良いことを簡単に書きます。
報告・連絡・確認
例えば塾講師である私に対して。
1ヶ月の計画通りに学習が進んでいない場合
**********************************************************************************:::
悪い例:7/30 生徒A「先生、やっぱり明日までにはこの単元は終わりません。」
私「なんでもっと早く言わないのおおおおお」
良い例:7/15 生徒B「先生、このペースだと31日までには終わりません。だから予定の半分の問題をこのスケジュールでやろうと考えているのですが、どう思われますか?」
私「それで!」
**********************************************************************************
解説します。
この悪い例と良い例の違いは、
ギリギリまで報告していないか、早めに終わらないことを予見して報告しているかです。
悪い例だと、もう締め切りが明日なのでどんな手も打ち用がありません。
しかし良い例は、まだ月の半分の時点で予定通りでないことを報告してくれているので、残りの時間をどう有意義に使うかを考える余地があります。
生徒Aの方は、おそらく生徒Bと同じく7/15にはもう終わらないペースであることがほとんどわかっていたはずで、その時すぐに私に報告、そして相談すべきだったと言えます。
さらに生徒Bの方は、自分の考えを提示しているところが良いです。
生徒Bは将来間違いなく仕事が早く終わる人になります。
家庭あるあるの例を書きましょう。
******************************************************************************
悪い例:親A「あんた学校から〇〇の案内もらってきてないの?」
生徒A「知らない」
親A 鞄ガサゴソ…「あっ、やっぱりあるたい!」
良い例:生徒B「ただいまー。」鞄ガサゴソ…「お母さんプリントー」
親B「はいどうもー」
******************************************************************************
違いは何でしょうか?
やはり良い例は行動が早いです。
いつまでも「親にプリントを渡す」というタスクを自分に溜め込まずにすぐに消化しています。
早いから忘れにくいですし、余計なタスクを持たないので自分のやるべきことに集中できます。
時間の使い方
集中といえば、勉強でもなんでも成果の出ない生徒は選択と集中に欠けます。
こんな経験はないでしょうか。
*****************************************************************************
生徒A「宿題たくさんあるからすぐにやらないと間に合わないかもしれないし徹夜になるかもしれない。かと言ってもやりたくないし遊んでからにしよう。」
別の日
生徒A「授業中だけど今先生見てないし、友達と隠れてゲームしよう。」
*****************************************************************************
どちらも一言で、「時間の使い方が下手」です。
やるべきことがあるのに遊んでいたら、ずっとそのことが頭にあるまま遊ぶことになってしまいませんか。
もしくは忘れていると自分に言い聞かせて。
もやもやしたまま遊んでいたら遊ぶことにも集中できないでしょう。
結果また遊びたくなるんですね。
授業中に遊ぶなんてバカの所業。
あなたがバカではない、行動がバカなんです。
授業中に遊んで内容がわからなくなって、それを授業時間以外で勉強する。
そんな無駄なことはありません。
それならば最初から授業に集中して、授業時間以外に思いっきり遊べば良いではありませんか。
遊んでいるようで成績が良い人ってそうしているんです。
遊ぶ時も勉強の時も、それぞれに集中しているんです。
時間の使い方が上手くなれば、余裕が生まれます。
余裕が生まれたら、豊かになります。