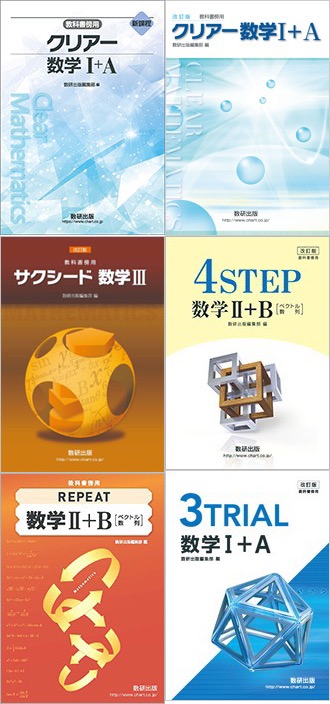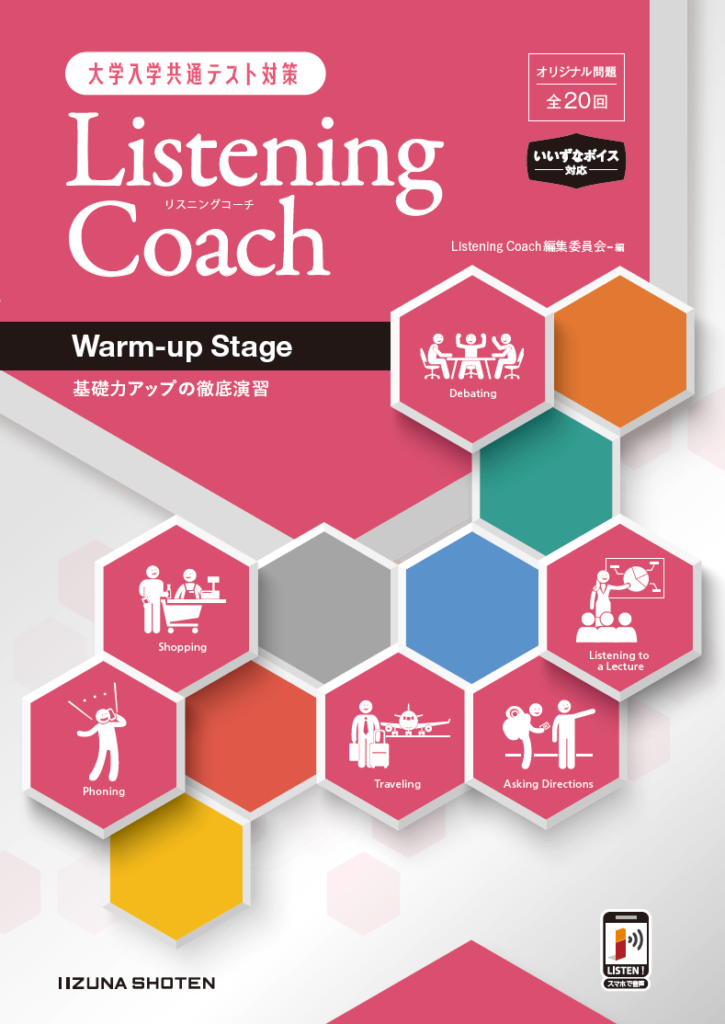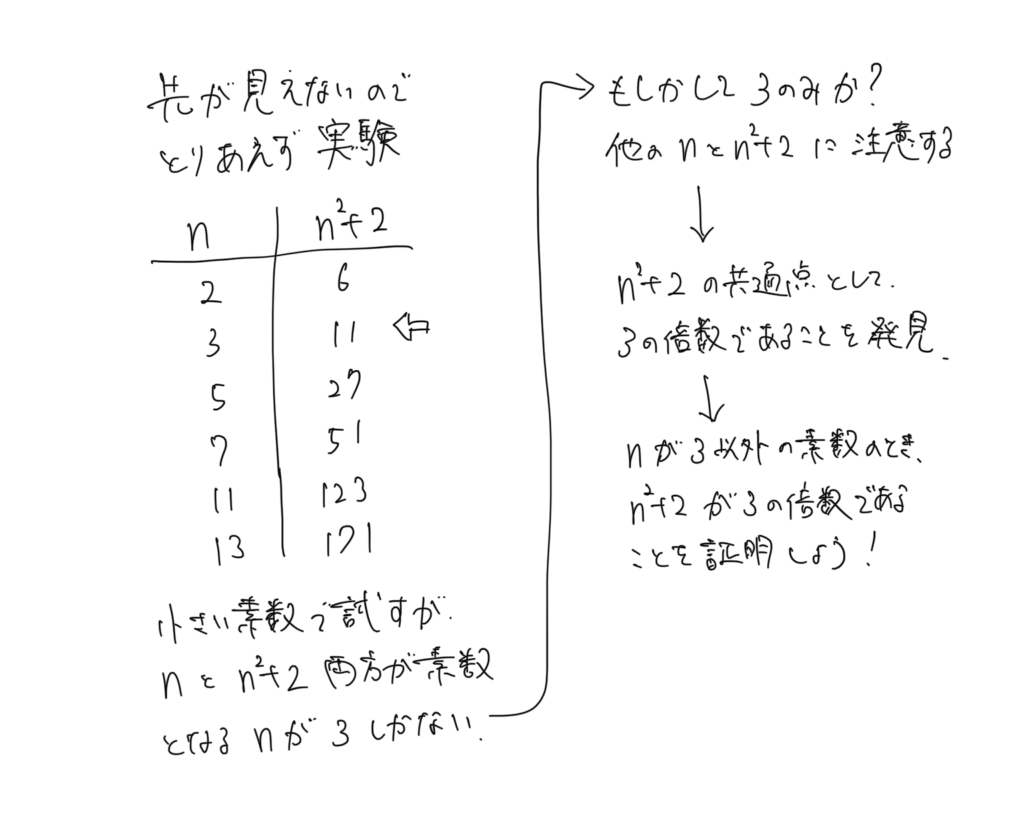公開日 2022/12/21
ものすごく寒くなりましたね。
12月に平地で雪が積もるのって長崎ではめずらしい気がします。
もう少し降ってくれれば雪合戦できるんですけどね。
雪遊びでも学べることはたくさんあります。
雪の冷たさを肌で感じます。
「0°Cで水は凍ります。」とテキストで学習するのとは違います。
靴下、靴を履いていても、地面から熱を奪われ足が霜焼けになります。
「熱は高い方から低い方へ移る。」と習うのとは違います。
机上では学べないことで溢れています。
大学生の時幾何学の授業を受けており、その時の教授がおっしゃったのですが、
「最近の学生は空間を見る力がない」
その当時(11年前です)の私は、「よくある『最近の若者は〜』の類だな」とか思ってたのですが、少しずつその言葉の意味が分かってきました。
11年前ー2011年ーといえば、東日本大震災の年です。
スマホが普及し始めた時期です。
イノベーター理論で言えば、インターネット利用者がレイトマジョリティーに入ったあたり?でしょうか。
つまり多くの人が手軽にインターネットを利用し始めた時期です。
私の世代が少年だったころから、子どもの遊び方は急速に変化していきました。
ほとんどが外で遊んでいたのが、室内遊びへと変わっていきました。
神社で遊んだり、山の中を駆け回ったり、道路でボール遊びしたり。
そこから少人数で部屋の中でゲームやネットで遊ぶようになりました。
子どもの変化ではなく、環境の変化です。
どこも人の手が加わっていき、伸び伸びと遊べる場が減りました。
公園で遊んでいるとうるさいと苦情がきますし(公園が狭いからですね)、ちょっと冒険しようとしたら不審者がいるから行くなと決めつけられます。道路で遊んだら危ないと叱られます。
道草食う暇もなく、学校は車で送り迎えです。
外で遊ばなくなって当然です。
空間認識力、という観点で見れば、
現代人のそれは低下傾向であると考えるのが自然です。
3次元空間よりも2次元平面を見ています。
子どもは家でしか遊べません。
外で人を観察すると、老若男女スマホとにらめっこです。
Googleマップやカーナビが目的地へ導いてくれます。
教授の言ったことが、徐々に分かってきますよね。
こういうことを考えていると、
世の中が便利になっていく分、ヒトの生物としての能力はだんだんと弱くなるのではないかと思います。地球上の他の生物と比べて、極めて異質な存在になるのかもしれません。
それって一体どうなんでしょう、という問いかけです。