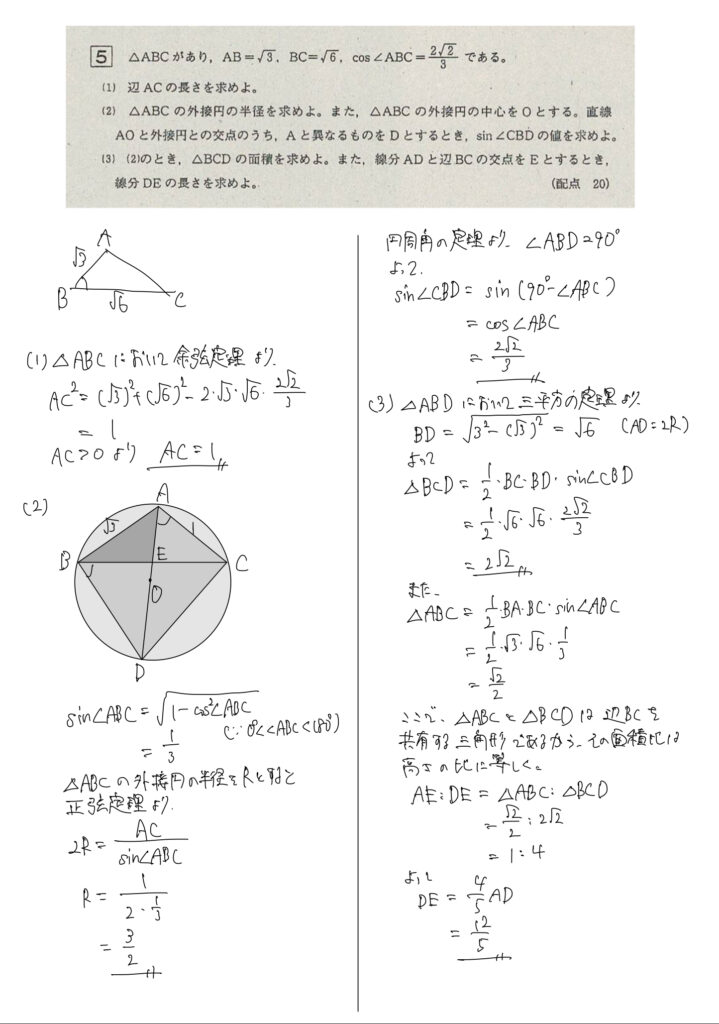公開日 2024/11/07
今年度から東洋大学で「学校推薦入試 基礎学力型」が始まったことは受験業界では有名です。
簡単に説明すると、推薦状がもらえたら2科目の試験を受けるだけでよく、志望理由書などの書類不要、面接もなし、12月に合否が分かる入試です。さらに併願可能。
もはや、推薦入試とは?というものですが、今後主に私立大学においてはこの動きは加速するでしょう。
現在国内には約800の大学があります。
その内私立大学、私立専門職大学は600ほどですが、その半分以上は入学者が定員割れとなっています。
学生集めに苦しんでいる大学は、様々な手を打ってきます。必然です。
この入試のように、早期に入学(候補)者を確保する施策が増えていくことはほとんど明らかです。
皆さんがおそらく考えることは、受験生の学力低下です。
易きに流れるのが人間ですから、このような制度に飛びつくのは想像に難くありません。
さすがに大学側もある程度の対策は打つはずで、合格・入学手続き後に宿題が課されることなどあるのだと思います。(調べてはいません)
しかし、2月の一般選抜まで戦ってきた受験生に及ぶことはないでしょう。(傾向です)
データによると、国公立大学は入学者のうちの一般選抜組は80%弱、上位国立大では90%超になります。
受験生本人の気持ちの話ではなく、12月で受験終了する場合と3月に終了する場合とでは、追い込み方が違いますから差が広がるのは当然のことです。
誤解されないように書いておくと、これは個人の話ではなく日本全体としてそのように向かっている、という話です。
受験生の学力差は広がっていきますが、同時に大学の方も格差が広がります。
ストレートに書いてしまいますが、お金さえ払えば入学できる学校はいくらでもあります。
そのような学校へ通う学生は何をやっているのか。少し考えたら分かります。
(学生の批判ではありません)
学生に迎合するような学校の存在意義とは?
淘汰されていくと思います。
とにかく勉強する
学生たちには勉強を頑張って欲しいと思います。
変に賢ぶって、悟ったフリをして、無気力になっていませんか。
もちろん社会のせいもありますが、そんなことを考えていても仕方がない。
まずはがむしゃらにやってみてはどうか。
無けなしの命がひとつ だうせなら使ひ果たさうぜ
獣ゆく細道 椎名林檎と宮本浩次