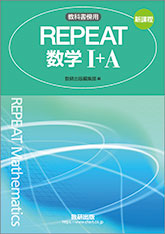公開日 2024/08/21
コミュニケーション力が必要などと言われますが、
果たしてそれを理解している人はどれくらいいるのか?
「コミュニケーション力」という言葉自体曖昧なものなので、
私の解釈の仕方の一つとして書いておきます。
まず前提として理解しておかねばならないことは、
コミュニケーションとは自分と相手、2者以上で成り立つということです。
例えば授業において、
「pq=-1は必要条件でしかないので、十分性を確認しなければならない」
みたいな説明をしたとして、
いくら講師側の知識が豊富で物事を理解する力に長けていたとしても、
生徒側が「必要条件」などを理解していないとそれが伝わらないということです。
当たり前のことのようですが、コミュニケーション力が「個人の能力」として語られる場合が多く、双方向という前提が抜け落ちている場合があるので注意したいところです。
becauseの使い方
コミュニケーションの齟齬が起きる例を紹介します。
「英文において『because』を文頭で使ってはいけないのか?」
という問いについて。
webを検索すると、次のような回答が得られます。
Because Mary is often late for the class, I don’t like her.
のような英文はよろしくない。通例、
I don’t like Mary, because she is often late for the class.
のように後ろに置く。
becauseは相手にとって新情報が含まれるときに用い、英文では旧→新の順に書くので後ろにするのが普通。
これは一見何も問題のない回答のようですが、
質問の答えになっていない可能性があることがわかるでしょうか?
上記の質問は、
「Because she is often late for the class.」
という英文を書いてはダメなのか、という問いであるかもしれません。
これに対する回答は、
「Becauseは接続詞であるから、主節と合わせて使う必要がある。ただし、口語では問題ない。」
となります。
このように、
同じ質問でも、その文章だけでは質問者の意図が完全には伝わっていないことがよくあります。
ちなみにchatGPTに同じ質問をして返ってきた回答は次のとおりです。
ーーーーーーここからーーーーーー
「because」を文頭に置くこと自体は文法的には間違いではありませんが、特定の文脈で適切かどうかが問題になります。文頭に「because」を置くと、その後に続く文が原因や理由を説明する副詞節となります。そのため、通常は主節(メインの文)とともに使用されます。
例えば、以下のような文は問題ありません:
- “Because it was raining, we canceled the picnic.”
ここでは、「Because it was raining」が理由を示す副詞節で、「we canceled the picnic」が主節です。
しかし、「Because」で始まる文が単独で使われると、不完全な感じになり、文法的には不適切とされることがあります。
例えば、「Because I was tired.」という文だけでは、主節がないため不完全な文になります。この場合、「Because I was tired, I went to bed early.」のように続けるのが正しい使い方です。
したがって、文頭に置くことは可能ですが、主節と一緒に使うことが重要です。
ーーーーーーここまでーーーーーー
一つの例に過ぎませんが、
これが「通じていない」ということです。
どのようにしたら回避できるでしょうか?
質問者目線では、
できるだけ詳細に状況を伝えることです。
今回の例では「前提」が重要です。
「becauseを文頭で使う」というのが曖昧だから、回答者はまず頭に浮かんだ「新旧情報の話」をしてしまいます。
逆に回答者側にできることも、
まず前提を確認する、ということです。
どのような文でbecauseを使うのか、という点を質問者に問うのが先です。
大抵の場合、質問者はそもそもどのような前提での話なのかを理解していません。
つまりコミュニケーション力というのは、
相手の話の背景を探りながら、また知識量・経験量などを見積もった上で応答する力であり、
この力は相手にも求められる、ということです。
ゆえに、
相手に話が通じないと感じる場合、自分自身も力不足であるということです。