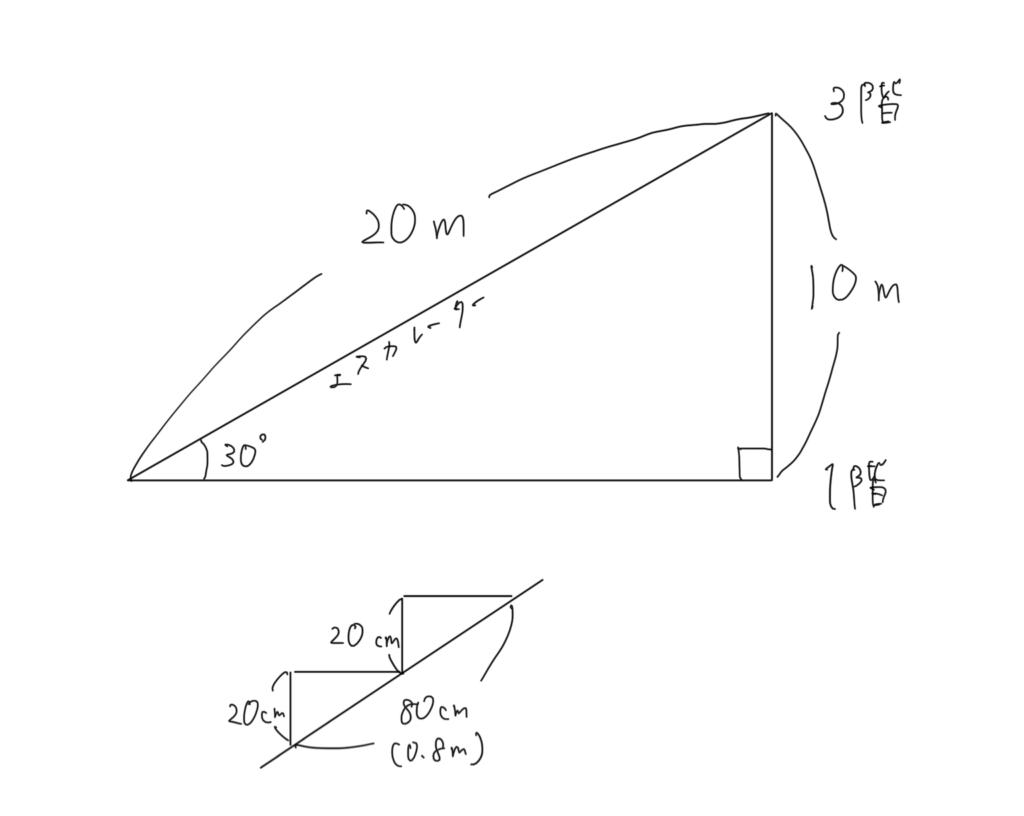公開日 2022/1/12
大学入学共通テスト直前です。
ほとんどの生徒はこのたった一回の試験でどの大学へ出願するかが決まります。
初めての大学入試なので、皆さんが経験したことのないことが起こります。
これまでの学校での模試は、
休み時間は10分とか15分だったと思いますが、
本番は50分ほどあります。
着席時間等を考えると30分から40分です。
この時間に何をするか考えているでしょうか。
勉強する?
それとも友達と話す?
動く
志望校合格を目指すのなら、この時間の過ごし方も適当ではいけません。
私のおすすめは、
身体を動かすことです。
試験時間は1時間以上です。
長いと2時間半は座りっぱなしです。
そりゃもう血流が悪くなるわけです。
血流が悪いことはすなわち頭が働かなくなることを意味します。
良いことはないです。
特に、第2の心臓と言われるふくらはぎを動かしましょう。
足を曲げて屈伸運動です。
休む
身体を動かすことに加えてもう一つのポイントがあります。
休み時間中は、リラックスし脳を休ませることです。
1時間以上、フル回転で働かせるのでしっかり休ませてあげましょう。
散歩しながら友達としゃべるのもよし。
ぼーっとするのもよし。
スマホは使わない
スマホは使わない
スマホは絶対に使わない
大事なことなので3回書きました。
スマホを使ったら、疲れます。
ネットなど見ようもんなら容赦ない情報攻撃が飛んできます。
あなたの脳は休めることなく次の試験時間を迎えるでしょう。
これは普段の勉強にも言えることですね。
休憩時間に使っていては、それは集中すべき時に集中できるわけがありません。
共通テスト当日は私も長崎大学にいます。
暇つぶしに話しかけてください。