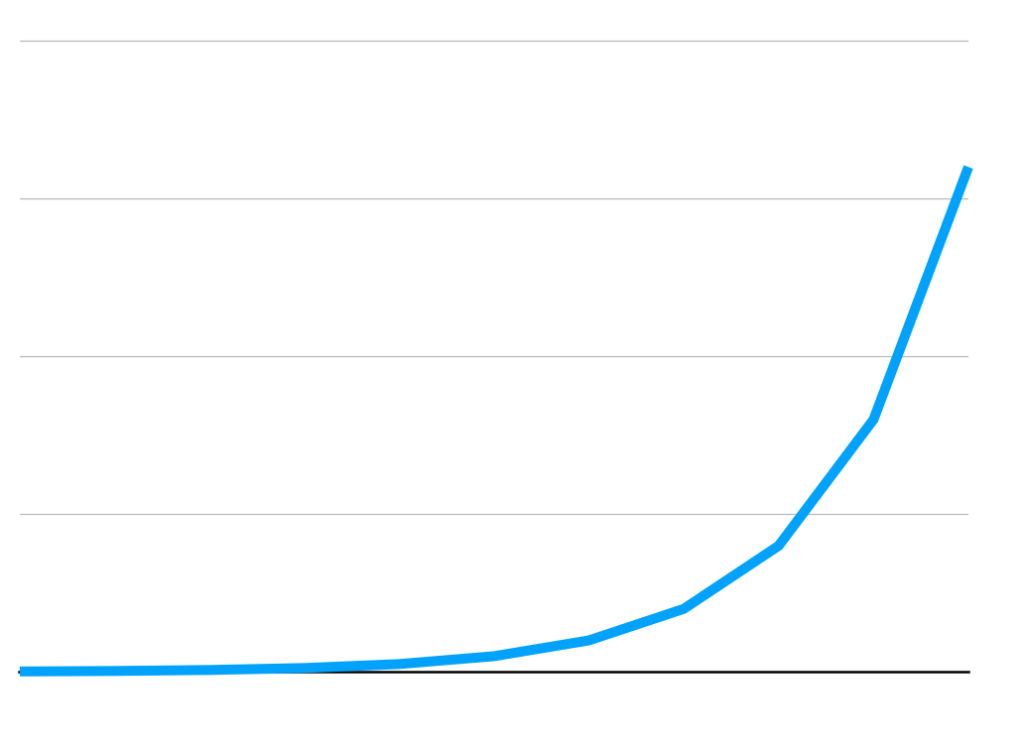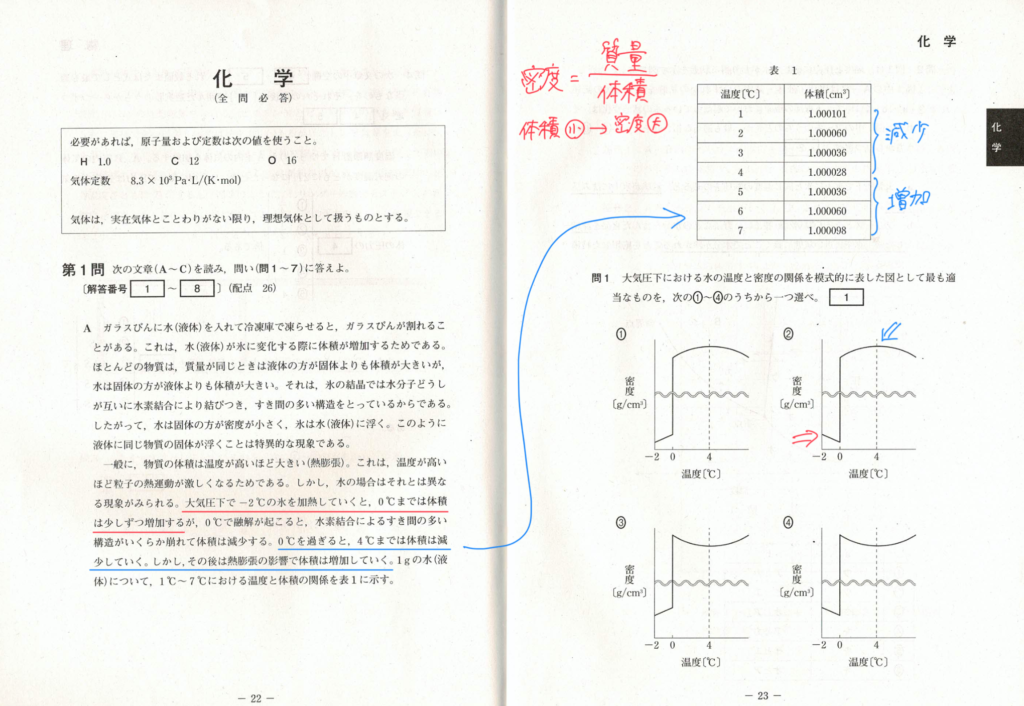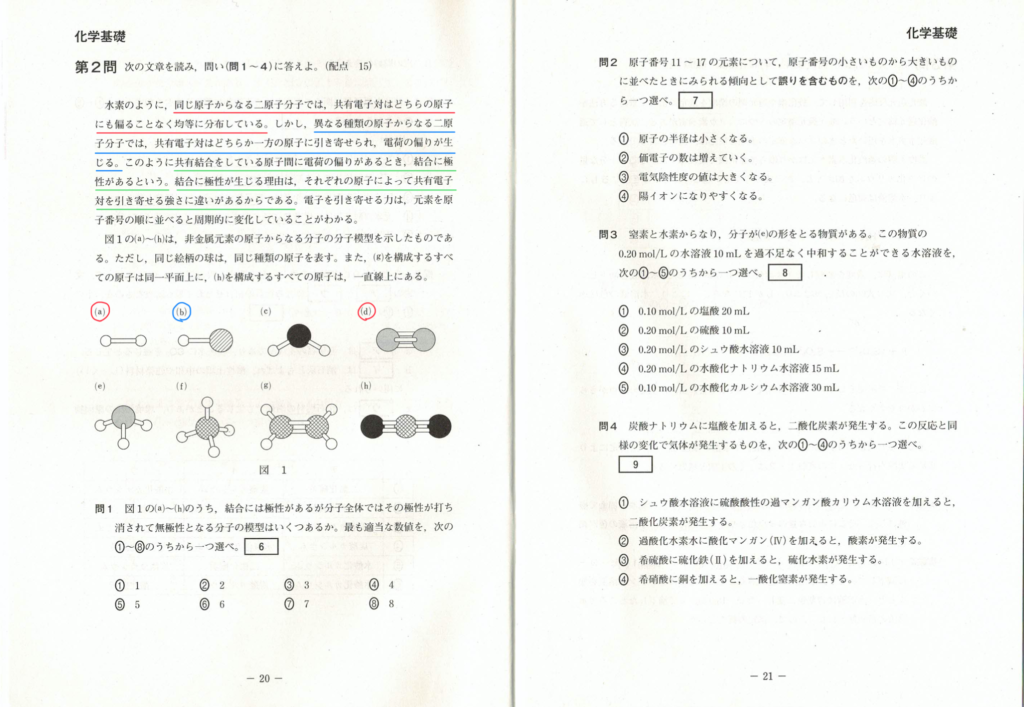公開日 2021/01/27
当事者とは、起きている問題を実際に体験している人。
当事者意識とは、簡単に言えばその問題を自分のこととして考えることです。
会社や学校など組織には
必ず当事者意識がある人、ない人がいると思います。
例えば、会社であれば
ある企画をするときに、様々なアイデアを出す人と、指示されたままに動く(あるいは動きもせずサボる)人がいます。
学校でも同じで文化祭などのイベントではそのように分かれますね。
この当事者意識、
学力を上げることについても、大きく影響していると思うんですね。
以前働いていた塾で、特に中学生に多かったです。
当然だとは思いますが、通塾を考えていらっしゃる方々は多くは、
「塾に通わせたい。」
とおっしゃられます。
そうです。
「通いたい」ではなく、「通わせたい」
なんですね。
すなわち、子の方に当事者意識がないということです。
この違いは、学力を伸ばせるかどうかの一つの大きなポイントだと考えます。
他人事のままでは、塾に来て勉強することは、「やらされていること」であり、自らの頭で考えることをしません。
考えることがなければ、勉強することは自分の意思に反していることなので続きませんし結果も出ません。
もちろん、素晴らしい先生はたくさんいますから、その先生のおかげで考え方が変わった、ということもあります。
自分で考えてもらうために
ではまだ精神年齢も低い中学生に
当事者意識を持たせるにはどのようにすれば良いのか。
これに対する答の一つは、
大人扱いすること、だと考えます。
自分の責任で行動してもらう、と言い換えることができます。
テレビなんかに出てくる子役は、同年代で比較するとものすごく大人びています。あれは、初めからそうだったわけではなく、周囲が皆年上で、大人と同等の扱いを受けているから自分で考える習慣がついているのではと思いますね。
少しズレますが、
赤ちゃんに赤ちゃんことばで話しかけるのはあまり良くないのでは、と思います。