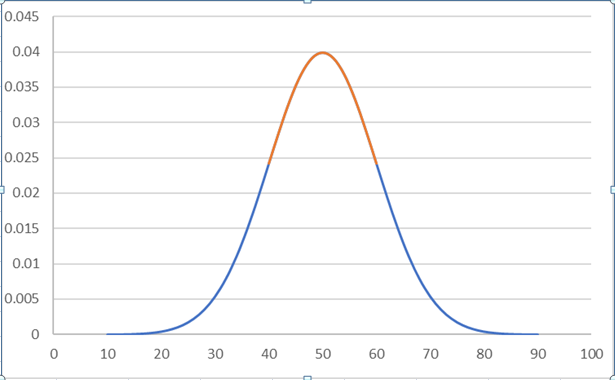最近よくスーパーでバナナを買って食べています。
バナナにはいろいろな炭水化物(糖質)が含まれています。それぞれ分子の大きさが異なり、小さいものから順に体内に吸収されていくので長時間エネルギーを補給できる優れものです。
日本食品標準成分表によれば、可食部100g中に炭水化物は22.5gで、そのうち(ここからは果物ナビから引用)ブドウ糖が2.6g、果糖が2.4g、ショ糖10.5g、でんぷん3.1gです。ブドウ糖(グルコース)と果糖(フルクトース)が単糖類で最も小さく、ショ糖(スクロース)は二糖類、でんぷんは多糖類、つまり高分子で吸収に時間がかかります。ちなみに一般的なバナナは一本100~150gで廃棄率40%。食べられる部分は一本当たり60~90gですね。
ここからマニアックな話なのでお好きな方だけどうぞ
脳の栄養源はブドウ糖ただ一つです。
成人の一日のブドウ糖消費量は120gだそうです。これを例えばバナナだけで摂ろうとすると、一本当たり1.56~2.34g摂れるので、おおよそ52~77本も食べなくてはなりません…というのは嘘で、ショ糖はブドウ糖1つと果糖1つ、でんぷんは複数のブドウ糖から成っているので、分解されるとブドウ糖になります。二糖の質量の単糖質量への換算係数は1.0526、でんぷんのそれは1.1111です(この辺の詳細は文科省へ)。つまり、(可食部100g中)ショ糖10.5gは単糖換算で
10.5×1.0526=11.0523g、
分子量の等しいブドウ糖と果糖の半分ずつに分かれるのでブドウ糖質量は
11.0523÷2=5.52615g
となります。またでんぷんのブドウ糖換算は
3.1×1.1111=3.44441g
です。よって、バナナ1本125g(可食部75g)とすると、それを食べて得られるブドウ糖は(2.6+5.52615+3.44441)×75÷100=8.67792g
となります。したがって、一日の消費量120gを摂るとなると、
120÷8.67792=13.82819846本
14本必要になります。これなら食べられそうですね…
もちろんそんなにバナナを食べる必要はなく、日本人の主なブドウ糖摂取源はご飯だと思います。精白米(うるち米)のご飯100g中にでんぷんは37.1g含まれています。これをブドウ糖換算すると
37.1×1.1111=41.22181g
です。よって300gのごはん、お茶碗2杯で一日の消費量を確保できることになります。ごはんすごい!
もちろんこれは脳での消費なのでそれ以外のためにもっと多く摂取する必要がありますし、消化吸収率を考慮していないので正確な数字ではありません。目安にしてください。
バナナの記事を書こうと思ったんですがお米すごいっていう記事になってしまいました。しかしここには書いてませんがバナナは他にもいろいろな栄養素が含まれています。私は引き続きバナナを食べます。食べろという意味ではありません。特に子どものうちは、いろいろなものをしっかり食べましょう。
追記:文科省リンク削除してます。検索すれば食品成分表は出てきます。