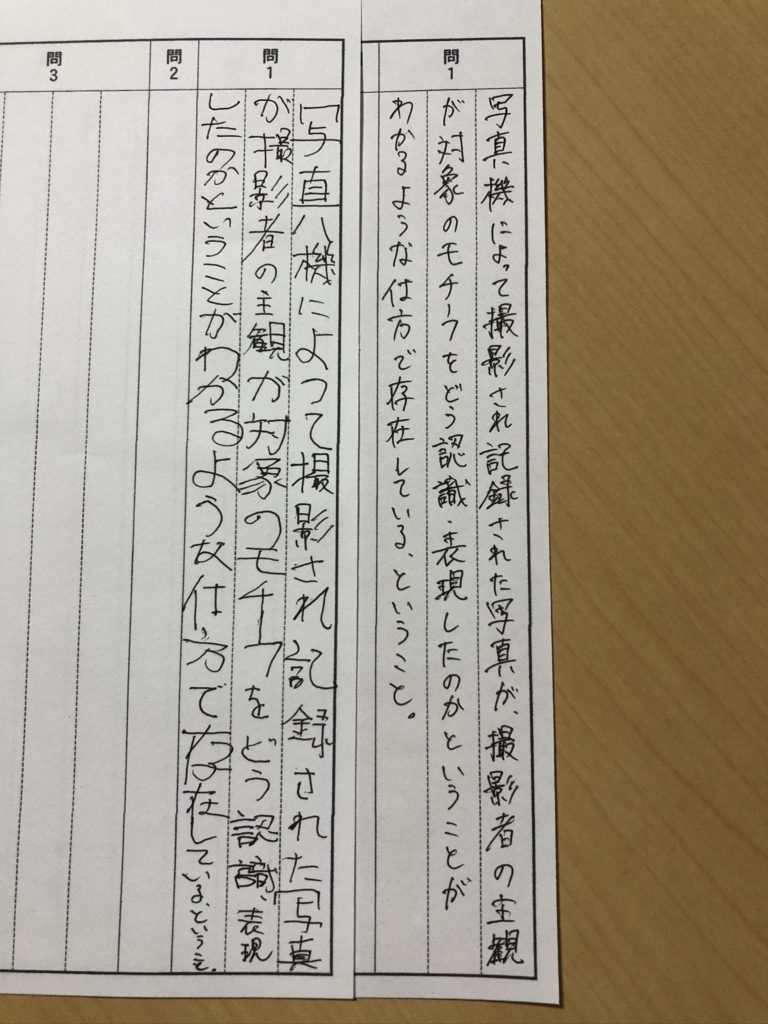公開日 2020/11/04
わかりにくいより、わかりやすい方が良い。
我々塾講師というのは、
常にわかりやすさを追求しています。
説明するときに
言葉を換えたり、何かに喩えたり、
ジェスチャーをしてみたり。
理解しやすくなるようにします。
生徒にとっても、わかりやすい方が良いです。
しかし、この「わかりやすさ」は、
注意すべき点があります。
わかりやすさの違い
ある説明がその人にとってわかりやすいかどうかは、
その人の既存の知識に大きく依存します。
例えば、
「正四面体ABCDの頂点Aから平面BCDへ下ろした垂線の足をHとする。」
という説明があったとき、
これを瞬時に理解するためには「正四面体」、「垂線の足」などという言葉の意味を知っておく必要があります。
これらを知らない人のための説明は、例えば
「すべての4つの面が正三角形でできた立体があり、その頂点をABCDとする。頂点Aから、三角形BCDに垂線を下ろし、その垂線と三角形BCDの交点をHとする。」
というふうになります。
さらに、「正三角形」を知らないのなら「3つの辺がすべて等しい三角形」という説明、「垂線」を知らないのなら「平面や直線などと90°で交わる直線」という説明を付け加える必要があります。
一番最初の一文の説明でわかる人と、
正三角形の説明まで必要な人には、かなりの知識量の差がありますね。
「わかりやすい」は、浅い時がある
以前、テストでは見えない学力差でも似た問題を出しましたが、
次の二次方程式を解け。 \[ x^{2}-4x-12=0 \]これの解き方は、
\[ x^{2}-4x-12=0 \] \[ (x+2)(x-6)=0 \] \[ x=-2 またはx=6 \]となります。
これの説明を、
「まず足してー4、かけてー12になる数字を見つける。その数字の組み合わせ2とー6の符号を換えたものが答えです。」
というと、特に習いたての中学3年生は「わかりやすい」と言います。
容易に答えが出せ、〇がつくからです。
しかし、これはただ簡単な答えの出し方を知っただけです。
応用の利かない、学力のつかない説明です。
「まず因数分解をする。」←因数分解ができることが前提
「(x+2)(x-6)=0 となるが、これはx+2とx-6の積が0に等しいという意味である。2数の積が0ということは、2数の内どちらかが0、または両方が0である。すなわち、x+2=0 または x-6=0 であり、x=-2,x=6 が解である。」
これが仕組みを理解でき、応用の利くものになりますが、
わかりにくい、と思う中学生もいると思います。
(前述のとおり、「因数分解」や「2数の積がゼロである条件」といった知識が必要になります。)
これを理解しないままだと、高校2年生で習う次のような問題への対処が遅れるわけです。
ほんの少しわかりにくいくらい
そもそも、人によってわかりやすさの基準は違いますから一概に言えませんが、
大体わかるけどちょっとだけわからない
くらいの説明を聞くのが最も効果的なのかもしれません。
自分にとって、難しすぎては聞く気も起こらないし、
簡単すぎては得るものが何もないからです。